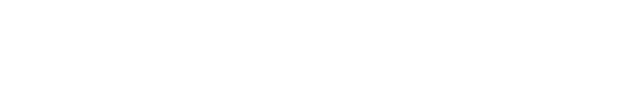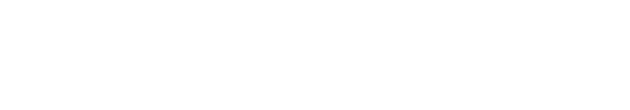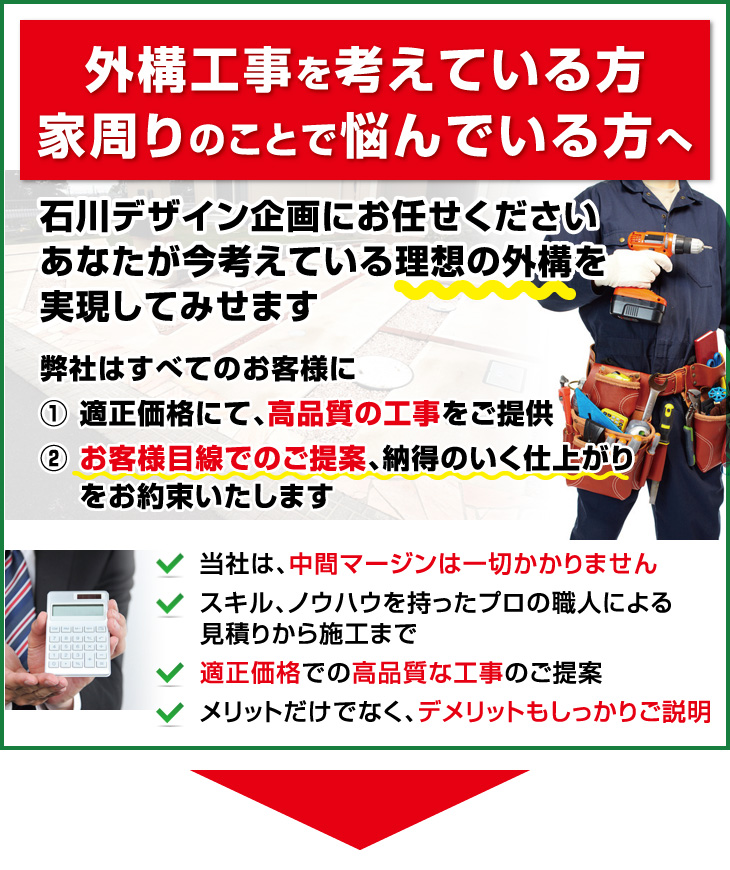コンクリート工事と聞くと、専門的で難しそうだと感じる方も多いのではないでしょうか。しかし、一戸建ての基礎やDIYでのアプローチ作りなど、意外と身近な場面でコンクリートは活躍しています。実は、いくつかのポイントさえ押さえれば、素人の方でも十分に挑戦できるのがコンクリート工事の面白いところです。
この記事では、「コンクリート工事が素人でもわかる!」をテーマに、材料の選び方から混ぜ方、打設のコツ、そして仕上げの注意点まで、基礎知識を徹底的に解説していきます。
目次
1.コンクリートって何?身近な材料のヒミツ

私たちは、日々の生活の中でコンクリートと様々な形で関わっています。
道路、橋、建物、ダムなど、私たちの社会基盤を支える上で欠かせない材料ですが、一体コンクリートとは何なのでしょうか?身近な材料の秘密に迫ってみましょう。
1-1.コンクリートの正体とは?
コンクリートは、主にセメント、水、そして骨材(砂や砂利)を混ぜ合わせて作られる人工の岩石のようなものです。
この3つの材料が混ざり合うことで、化学反応が起こり、時間とともに硬化して、非常に丈夫な塊へと変化します。
1-2.セメントが必要な理由とは?
コンクリートの主役とも言えるのがセメントです。
セメントは、石灰石や粘土などを高温で焼き、粉砕して作られます。このセメントが水と混ざると、水和反応という化学反応を起こし、糊のように骨材同士を結合させます。
この結合力が、コンクリートの強度を生み出す源になります。
1-3.骨材の役割とは?
コンクリートの約7割を占めるのが骨材です。
骨材には、粒の小さい細骨材(砂)と、粒の大きい粗骨材(砂利や砕石)があります。骨材はコンクリートの体積を大きくするだけでなく、硬化する際の収縮を抑えたり、強度を高めたりする役割があります。
また、セメントの量を減らすことで、コストダウンにも貢献しています。
もし骨材がなければ、コンクリートは硬化する際にひび割れてしまったり、強度が不足してしまったりするのです。
1-4.水の意外な役割
「水」は、セメントが硬化するために必要な化学反応を促すだけでなく、セメントと骨材を均一に混ぜ合わせるための「潤滑剤」のような役割も果たしています。
適切な量の水を加えることで、作業しやすい柔らかさになり、型枠に流し込みやすくなります。しかし、水が多すぎると強度が低下し、少なすぎると作業性が悪くなるため、水の量は非常に重要です。
1-5.身近なコンクリートの進化
コンクリートは、紀元前の古代ローマ時代から使われていたと言われています。
パンテオンのような壮大な建造物も、コンクリートの原型が使われていたと考えられています。そして現代では、より高性能なコンクリートが開発されています。
例えば、非常に強度が高い高強度コンクリートや、ひび割れに強い繊維補強コンクリート、さらには、光触媒の働きで汚れがつきにくい自己洗浄コンクリートなど、様々な機能を持つコンクリートが登場しています。
2.なぜコンクリート工事が必要なの?その役割とメリット

コンクリート工事は、私たちの生活を支える上で欠かせない基盤であり、その役割とメリットは多岐にわたります。
なぜコンクリート工事が必要なのか、その重要性について詳しく見ていきましょう。
2-1.コンクリートの持つ優れた特性
コンクリートはセメント、水、砂、砂利を混ぜ合わせて作られる人工の岩石です。このシンプルな組み合わせが、驚くほど優れた特性を生み出します。
まず、圧縮強度が高いことが挙げられます。上からの力に対して非常に強く、高層ビルや橋、ダムといった巨大な構造物の荷重をしっかりと支えることができます。地震の多い日本において、この強度は建物の安全性を確保する上で非常に重要です。
次に、耐久性、耐候性、不燃性に優れている点も大きなメリットです。風雨や紫外線、温度変化といった自然の影響を受けにくく、長期間にわたってその性能を維持します。また、火災にも強く、燃えにくい性質があるため、建物の防火性能を高める上でも貢献します。
さらに、自由な形状に成形できることもコンクリートの大きな利点です。流動性があるため、型枠に流し込むことで複雑な形状やデザインにも対応できます。これにより、建築物の多様な設計要求に応え、美しい景観を作り出すことも可能です。
2-2.コンクリート工事の主な役割
コンクリート工事は、私たちの身の回りにある様々な構造物を支える基盤として、多岐にわたる役割を担っています。
2-2-1.建築物の基礎・構造体
住宅、オフィスビル、商業施設など、あらゆる建築物の土台となる基礎や、建物を支える柱や梁、壁、床といった構造体にコンクリートは不可欠です。地震や風などの外部からの力に耐え、建物の安全性を確保するために、コンクリートの強度が最大限に活かされています。
2-2-2.社会インフラの整備
道路や橋、トンネル、ダム、堤防、下水道といった社会インフラの整備にもコンクリートは欠かせません。これらのインフラは、私たちの生活や経済活動を円滑に進める上で基盤となるものであり、コンクリートの耐久性と強度なしには成り立ちません。特に、水害から地域を守る堤防やダム、交通網を支える橋やトンネルは、コンクリートの高い信頼性が求められます。
2-2-3.防災・減災対策
地震や津波、洪水などの自然災害から人々の生命や財産を守るための防災・減災施設にもコンクリートは多く用いられます。防波堤や津波避難ビル、耐震補強など、コンクリートの持つ高い強度と耐久性が、災害に強い社会を構築するために不可欠です。
3.コンクリート工事のメリット

コンクリート工事を行うことには、多くのメリットがあります。
ここでは具体的なメリットについて詳しく解説していきます。
3-1.高い安全性と耐久性
前述の通り、コンクリートの最も大きなメリットは、その高い安全性と耐久性です。これにより、建造物の長寿命化を実現し、メンテナンスコストの削減にもつながります。
3-2.コストパフォーマンス
コンクリートは、比較的安価に入手できる材料であり、施工も安定しています。そのため、大規模な建設プロジェクトにおいても、優れたコストパフォーマンスを発揮します。
3-3.環境への配慮
セメントの製造過程でCO2排出がある一方で、コンクリートはリサイクルが可能であり、長寿命であることから、ライフサイクル全体で見た場合の環境負荷を低減できる可能性があります。近年では、環境配慮型のコンクリートも開発されています。
4.コンクリート工事の基礎の流れ

この項では、コンクリート工事の基礎の流れについて解説していきます。
4-1.型枠(かたわく)の組み立て
まず最初に行うのが、型枠の組み立てです。これは、コンクリートを流し込むための「器」を作る作業です。設計図に基づいて、木材や鋼製のパネルを正確に組み立て、コンクリートが漏れ出さないようにしっかりと固定します。この型枠の精度が、コンクリート構造物の仕上がりの良し悪しを左右するため、非常に重要な工程です。
4-2.鉄筋(てっきん)の組み立て・配筋(はいきん)
次に、鉄筋の組み立て、いわゆる「配筋」を行います。コンクリートは圧縮に強いですが、引っ張りには弱いという性質があります。そこで、引っ張る力に強い鉄筋をコンクリート内部に配置することで、構造物全体の強度を高めます。設計図通りに鉄筋を配置し、結束線などでしっかりと固定していきます。この配筋作業も、構造物の安全性を確保するために非常に重要な工程です。
4-3.コンクリートの打設(だせつ)
型枠と鉄筋の準備が整ったら、いよいよコンクリートの打設です。ミキサー車で運ばれてきた生コンクリートを、型枠の中に流し込みます。この際、コンクリートポンプ車などを使って、高い場所や広い範囲にも均一にコンクリートを送り込みます。コンクリートを流し込む際には、バイブレーターという機械を使って振動を与え、コンクリート内部の空気を抜き、密実なコンクリートにする必要があります。これを「締固め(しめかため)」と呼びます。
4-4.養生(ようじょう)
コンクリートを打設した後も、大切な工程が残っています。それが養生です。打設されたばかりのコンクリートは、まだ固まりきっていません。乾燥や急激な温度変化から保護し、十分な強度を発現させるために、一定期間、水を与えたり、シートで覆ったりします。この養生期間中に適切な管理を行うことで、コンクリート本来の性能を最大限に引き出すことができます。
4-5.型枠の解体(かいたい)
コンクリートが十分に固まり、設計通りの強度に達したら、型枠を解体します。慎重に型枠を取り外すと、コンクリート構造物の姿が現れます。この後、必要に応じて表面の仕上げ作業などが行われ、コンクリート工事は完了となります。
5.知っておきたい!コンクリートの種類と特徴

まず、最も一般的なものが「普通コンクリート」です。セメント、水、砂、砂利を混ぜて作られ、圧縮に強く、耐久性にも優れるため、建築物の基礎や構造部材など、幅広い用途で利用されています。皆さんが普段目にされるコンクリートの多くは、この普通コンクリートです。
次に、「高強度コンクリート」があります。普通コンクリートよりも高い圧縮強度を持つコンクリートです。特殊な混和材料を加えたり、密実な配合にすることで実現されます。高層ビルや長大橋など、より大きな荷重を支える必要がある構造物に使用され、部材の断面を小さくできるため、設計の自由度を高めるメリットもあります。
「軽量コンクリート」は、砂利の代わりに軽量骨材(人工軽量骨材や発泡スチロールなど)を用いたコンクリートです。普通コンクリートに比べて比重が小さく、建物の自重を軽減できるため、高層建築物や免震・制震構造に有効です。また、断熱性や遮音性に優れるという特徴も持ち合わせています。
また、「マスコンクリート」という種類もあります。これは、ダムや大規模な基礎など、非常に厚いコンクリート構造物を打設する際に用いられます。セメントの水和熱による温度上昇を抑えるため、低発熱型のセメントを使用したり、冷却管を埋設するなどの工夫が施されます。ひび割れの発生を防ぎ、構造物の健全性を保つために重要な技術です。
特殊なコンクリートとしては、「プレキャストコンクリート」も挙げられます。これは、工場であらかじめ製造されたコンクリート部材のことです。現場での作業を効率化し、品質管理を徹底できるため、工期の短縮やコスト削減に貢献します。トンネルのセグメントや建築物の壁パネルなど、多くの場所で活用されています。
6.プロに頼む?自分でやる?工事依頼のポイント

自宅のメンテナンスやリフォームを検討する際、「プロに依頼すべきか、それともDIYで済ませるか」という疑問に直面することは少なくありません。どちらを選ぶかは、工事の種類、自身のスキル、そして費用のバランスによって大きく変わってきます。
まず、専門的な知識や技術が必要な工事、安全に関わる工事は迷わずプロに依頼するべきです。例えば、電気工事、水回りの配管工事、ガス設備の設置、屋根の修理などは、安易なDIYが事故や後々の大きなトラブルにつながる可能性があります。また、法律や条例で定められた資格が必要な工事もありますので、事前に確認が必要です。プロに依頼すれば、適切な施工はもちろんのこと、万が一の際の保証やアフターサービスも期待できます。
一方で、比較的簡単な作業や、専門知識が不要な範囲であればDIYも有効な選択肢です。壁紙の張り替え、ペンキ塗り、簡単な棚の設置、庭の手入れなどは、自身のペースで作業を進められ、何よりも費用を抑えることができます。DIYを通じて、自宅への愛着も一層深まるでしょう。ただし、工具の準備や材料の選定、作業時間の確保など、意外と手間がかかることも考慮に入れる必要があります。
プロに依頼する場合のポイントは、複数の業者から見積もりを取り、比較検討することです。見積もりの内容だけでなく、工事実績、担当者の対応、保証内容なども総合的に判断しましょう。焦らず、信頼できる業者を見つけることが成功の鍵です。また、工事内容について疑問点は積極的に質問し、納得した上で契約を進めることが大切です。
まとめ.

今回はマイホームの基礎を学ぶ!知っておきたいコンクリート工事のポイントを紹介してきました。
コンクリートにはいくつかの種類があります。それぞれの仕様は用途によって異なりますが、是非参考にしてみてください。
今回紹介したコンクリート工事のポイントを押さえておくことが大切です。自分で工事をすることも良いことではありますが、失敗のリスクがありますので大きい工事はお近くの専門業者へ依頼することをおススメします。
筆者:外構工事職人歴20年・石川