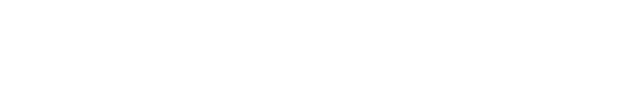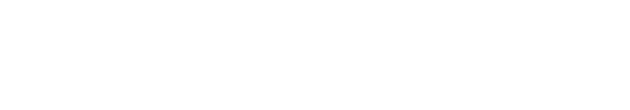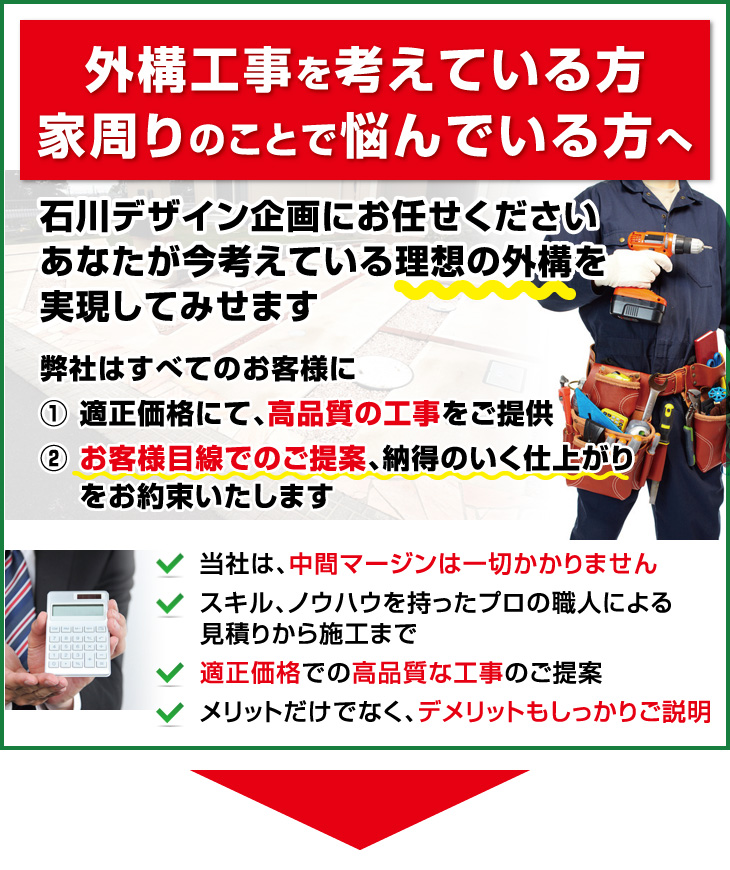ブロック塀は外構の目隠しなどに役立ちますが、台風や大雨の影響を受けて倒壊する危険性もあります。
ブロック塀は重量があるため倒壊すると周辺に大きな被害を及ぼす可能性があり、事前にしっかり対策をしておくことが大切です。
本記事では、ブロック塀の台風・大雨対策を紹介します。
火災保険が適用される条件なども詳しく解説しているので、参考にしていただけると幸いです。
目次
1.ブロック塀設置前の大雨・台風対策5選
 ブロック塀は住宅や庭の安全性を守る重要な設備ですが、台風や大雨時には倒壊や亀裂のリスクがあります。そのため設置前から対策を考えておくことが大切です。
ブロック塀は住宅や庭の安全性を守る重要な設備ですが、台風や大雨時には倒壊や亀裂のリスクがあります。そのため設置前から対策を考えておくことが大切です。
設置時の対策としては、以下のような内容があります。
- 十分な基礎と地盤の強化
- 控え壁・控え柱の設置
- ブロックの強度・種類の選定
- 排水を考慮した設計
- 正確性の高い施工精度
ブロック塀設置時には、台風や豪雨に耐える構造を意識した設計・施工が求められます。
このような対策を実施すれば、台風や大雨時の安全性が向上し、倒壊による被害や修理費用を大幅に減らすことが可能です。
それぞれのポイントを詳しく解説します。
1-1.十分な基礎と地盤の強化
ブロック塀の耐久性を左右するのは、基礎と地盤の強さです。大雨で地盤が緩むと塀全体が傾いたり、台風の強風で倒壊する危険性があります。
そのため、設置前には地盤改良や十分な深さのコンクリート基礎の施工が必要です。
地盤を固めることで支柱やブロックの安定性が向上し、強風や豪雨にも耐えやすくなります。
また、地盤沈下を防ぐことで、長期的な安全性を確保でき、災害時のリスクを大幅に減らせます。
1-2.控え壁・控え柱の設置
ブロック塀の倒壊を防ぐためには、控え壁や控え柱を設置することが効果的です。
高さのある塀や風を受けやすい場所では、支えとなる控え構造がないと台風の強風や豪雨による圧力で容易に倒れてしまいます。
控え柱や控え壁を入れることで塀全体の強度が向上し、局所的な荷重が分散されるため、被害を最小限に抑えることが可能です。
1-3.ブロックの強度・種類の選定
ブロック塀の耐久性は使用するブロックの強度や種類によって大きく変わります。
通常のコンクリートブロックよりも耐圧性や耐風性に優れたものを選ぶことで、台風や大雨時の倒壊リスクを減らせます。
空洞ブロックや軽量ブロックは施工が簡単ですが、強度が不足しやすいため、高さや設置環境に応じて選ぶ必要があります。
1-4.排水を考慮したい設計
大雨時にブロック塀が被害を受ける原因の一つが、水の滞留です。
塀の周囲に水が溜まると、基礎が緩んで傾きや倒壊につながります。
そのため設置前には、雨水が流れやすい排水計画を考慮することが大切です。塀の傾斜を工夫したり、側溝や排水溝を設置したりすることで水はけを良くし、基礎の安定性を保つと安心です。
1-5.正確性の高い施工精度
ブロック塀の耐久性を高めるには、設計通りの精度で施工することが大切です。
水平や垂直がずれていたり、ブロック同士の接合が不十分だと、台風や大雨で受ける風圧や水圧に耐えられず、倒壊や亀裂の原因になります。
施工時には水準器やレーザーを用いて正確な施工を行い、基礎とブロックの接合部も強固に固定することが大切です。
2.今すぐ修繕すべきブロック塀の特徴
 昨今、劣化したブロック塀の倒壊による被害が相次いでおり、それに合わせて法律も整備されています。
昨今、劣化したブロック塀の倒壊による被害が相次いでおり、それに合わせて法律も整備されています。
古いブロック塀をそのままにしていて万が一被害が出た場合、法的に不利になる可能性が高いです。
以下の点が見られるブロック塀は、今すぐ修繕、改修を検討する必要があります。
- 2.2メートル以上の高さがある
- 控え壁が設置されていない
- ひび割れや傾きがある
それぞれの点を詳しく解説します。
2-1.2.2メートル以上の高さがある
古いブロック塀が倒壊し、過去にその下敷きになり死者が出た例があります。
それを踏まえて、現在建築基準法ではブロック塀の高さは2.2メートルまでと定められました。
ただし建築基準法が見直される前に設置されたブロック塀はこれより高さがある可能性も高いです。
また、そのようなブロック塀はかなり古く、劣化が進んでいる可能性も高いです。
長く同じブロック塀を使い続けているという家庭は、今すぐブロック塀の高さを確認し、必要であれば新しい法律を遵守したものに取り替えることが大切です。
2-2.控え壁が設置されていない
控え壁や控え柱がないブロック塀は、台風や大雨時に倒壊する危険性が高まります。
控え壁は塀の背面から支える役割を持ち、風圧や地盤の揺れによる負荷を分散させます。控え構造がない場合、とくに高さのある塀は支柱や基礎に大きな負荷が集中し、ひび割れや傾きが発生しやすくなります。
設置後に控え壁がないことが判明した場合は、早急に専門業者に相談し、補助構造を追加するなどの修繕を検討することがおすすめです。
2-3.ひび割れや傾きがある
ブロック塀にひび割れや傾きが見られる場合は、台風や大雨による倒壊リスクが非常に高いため、早急な修繕が必要です。
ひび割れは塀内部の応力や基礎の劣化を示すサインであり、傾きは地盤や基礎の不安定さを意味します。
とくに通行人や隣家への被害が懸念される場合は、専門業者に点検・補修を依頼し、必要に応じて塀の補強や再施工をしてもらう必要があります。
3.大雨・台風に強いブロック塀の種類は?
 大雨や台風が頻発する日本では、家を守るフェンスやブロック塀の強度が暮らしの安全に直結します。とくに強風や豪雨により、老朽化したブロック塀が倒壊する事故は毎年のように発生しています。
大雨や台風が頻発する日本では、家を守るフェンスやブロック塀の強度が暮らしの安全に直結します。とくに強風や豪雨により、老朽化したブロック塀が倒壊する事故は毎年のように発生しています。
そのため、大雨や台風に強いブロック塀を設置することも大切です。以下のような種類を選び、台風や大雨対策を強化する必要があります。
- 鉄筋コンクリート(RC)ブロック塀
- 控え壁・控え柱付きブロック塀
- 軽量コンクリートブロック塀
- 既製の耐風・耐震ブロック塀パネル
- 目地スリット・通気スリット付きブロック塀
それぞれの種類の特徴を詳しく解説します。
3-1.鉄筋コンクリート(RC)ブロック塀
鉄筋コンクリート(RC)ブロック塀は、台風や大雨に強い構造として高い評価を得ています。
内部に鉄筋をしっかりと組み込み、コンクリートで固めることで、強風や地震などの強い力に対しても優れた耐久性を発揮してくれます。
通常のブロック塀よりも施工にコストはかかりますが、長期的に見ればメンテナンス頻度を減らせるため、結果的に経済的ともいえます。
大雨による地盤の緩みにも強い設計が可能なため、自然災害が多い地域ではとくにおすすめの選択肢といえます。
3-2.控え壁・控え柱付きブロック塀
控え壁や控え柱を取り入れたブロック塀は、強風に対して倒れにくい構造になっています。
台風時には横方向からの強い風圧が加わりやすく、とくに高さのあるブロック塀はリスクが増します。一定間隔で控え壁や控え柱を設置すれば、塀を後ろから支える効果が生まれ、強度が格段に向上します。
大雨によって地盤が緩んだ場合でも、補強された構造が倒壊を防ぎやすくなります。
建築基準法でも規定されている安全対策であり、台風や大雨に強いブロック塀を選びたい方にはとくにおすすめです。
3-3.軽量コンクリートブロック塀
軽量コンクリートブロックは、通常のブロックよりも軽いため、倒壊時の危険性を軽減できるのが大きな特徴です。
台風や大雨でブロック塀が倒れると大事故につながることがありますが、軽量素材であれば被害を最小限に抑えやすいです。
施工時の負担が少なく、基礎への荷重も軽減されるため、地盤が弱い場所や排水性の悪い土地でも導入しやすいメリットがあります。
3-4.既製の耐風・耐震ブロック塀パネル
最近では、既製の耐風・耐震ブロック塀パネルも注目されています。
台風時に想定される風圧や大雨による浸水被害を考慮し、強度試験をクリアした製品も多く、安心して設置できます。
また、施工時間が短縮できるため工期の短さも魅力です。
デザインバリエーションも豊富で、フェンスのような軽やかな見た目から、重厚感ある外構まで対応可能です。
3-5.目地スリット・通気スリット付きブロック塀
大雨や台風に強いブロック塀として近年注目されているのが、目地スリットや通気スリットを設けたタイプです。
通常のブロック塀は風をまともに受け止めてしまうため、強風時に大きな負荷がかかります。
しかし、スリットがあることで風が抜け、圧力を分散できるため、倒壊のリスクが大幅に低減されます。
さらに、大雨の際には通気性や排水性が確保され、湿気や水圧の影響を受けにくくなります。
4.大雨・台風でブロック塀が倒壊したときはどうする?
 実際にブロック塀が大雨や台風の被害を受けて倒壊した際は、速やかな対応が求められます。
実際にブロック塀が大雨や台風の被害を受けて倒壊した際は、速やかな対応が求められます。
ただし間違った対応をすると後々後悔することになるので、以下のステップを確認する必要があります。
- 周辺の安全を確保する
- 被害状況を確認する
- 倒壊部分の記録を残す
- 応急処置をする
- 保険の条件を確認する
それぞれのチェックポイントを詳しく解説します。
4-1.周辺の安全を確保する
ブロック塀が台風や大雨で倒壊すると、思わぬ二次災害が発生する恐れがあります。
とくに道路や隣家に面している場合は、通行人や車両に被害を及ぼす可能性が高いため、まずは周辺の安全確保を行う必要があります。
崩れかけのフェンスやブロック片が残っている場合、強風が続けばさらに飛散する危険もあるため、カラーコーンやロープで立ち入り禁止の範囲を明示するのがおすすめです。
安全が確認されるまでは、自分で不用意に瓦礫を動かさず、必要であれば消防や自治体に連絡して専門的な処置を依頼することも大切です。
4-2.被害状況を確認する
周辺の安全を確保した後は、ブロック塀やフェンスの被害状況を落ち着いて確認することが大切です。台風や大雨の直後は地盤が緩みやすく、外見では無事に見える部分でも内部の鉄筋が曲がっていたり、基礎が沈下していたりすることがあります。
目視だけでなく、手で軽く揺らしてみて異常がないかをチェックするとより確実です。ただし、自分で危険を伴う調査を行うのは避け、専門業者に依頼するのが安心です。
4-3.倒壊部分の記録を残す
台風や大雨でブロック塀が倒壊した場合、修復や保険申請に備えて記録を残すことが欠かせません。現場の写真や動画は、被害の客観的証拠となり、後に施工業者へ正確な状況を伝える際にも役立ちます。
撮影する際は倒壊部分だけでなく、周辺のフェンスや敷地の様子も含めて複数の角度から残すのがポイントです。
また、崩れたブロックの個数や位置関係をメモしておくと、工事の見積もりや保険会社の査定がスムーズになります。
4-4.応急処置をする
倒壊したブロック塀は放置すると危険が増すため、可能な範囲で応急処置を行う必要があります。たとえば、大きなブロック片を安全な場所に移動させたり、ブルーシートをかけて雨水の浸入を防いだりすると被害拡大を抑えられます。
また、フェンスが破損して外からの視線が気になる場合には、仮設フェンスやネットを設置するのもおすすめです。
4-5.保険の条件を確認する
ブロック塀が台風や大雨で倒壊した際には、加入している火災保険や地震保険の補償対象となるかを確認することも大切です。一般的に火災保険には風災や水災が含まれていることが多く、強風や豪雨による損害は補償を受けられるケースがあります。
ただし、補償対象は建物本体に限られる場合や、外構が含まれる場合など契約内容によって異なるため、契約書をよく確認する必要があります。
保険金を受け取るためには倒壊部分の写真や修理見積もりが必要になるため、被害記録を早めに準備しておくとスムーズです。
5.大雨・台風によるブロック塀の倒壊には火災保険は適用するの?
 一般的な火災保険は火事だけでなく、台風や豪雨などの自然災害による損害も対象です。ただし、すべての保険で自動的に適用されるわけではなく、契約内容や特約の有無によって補償範囲が異なります。
一般的な火災保険は火事だけでなく、台風や豪雨などの自然災害による損害も対象です。ただし、すべての保険で自動的に適用されるわけではなく、契約内容や特約の有無によって補償範囲が異なります。
以下の点をチェックして、適切な補償を受けられるようにしておくことが大切です。
5-1.自然災害による損害なら適用されることが多い
火災保険は名前の通り火災に備えるためのものですが、実際には台風や大雨といった自然災害による損害にも対応しているケースが多くあります。
たとえば、強風でブロック塀やフェンスが倒壊した場合、風災として補償を受けられる可能性があります。
同様に、大雨による土砂崩れや浸水で塀が破損した場合、水災補償が適用されることがあります。
5-2.風災補償・水災補償がついているか確認する
ブロック塀やフェンスが台風や大雨で倒壊した場合、保険が適用されるかどうかは契約内容に大きく左右されます。
とくに重要なのが風災補償と水災補償です。
風災補償があれば、台風や強風によって塀が崩れた際に修理費用が補償されます。
一方で水災補償は、豪雨や洪水による土砂崩れや浸水で外構が破損した際に適用されます。
保険会社によっては、どちらか一方しか付帯していないケースもあり、両方を備えておくと安心です。
5-3.ブロック塀も補償範囲に含まれているか確認
火災保険に加入していても、ブロック塀やフェンスが必ず補償対象になるとは限りません。
多くの保険では建物本体は補償範囲に含まれますが、外構部分は付帯物として扱われ、条件によって対象外となることがあります。
もし対象外であれば、特約を追加することで補償を広げられるケースもあります。台風や大雨で倒壊した場合、修理費用は数十万円以上に及ぶこともあるため、事前の確認は将来の大きな出費を抑えるためにも大切です。
5-4.免責額以下の場合は保険金が出ないことが多い
火災保険には「免責額」という自己負担分が設定されている場合があり、この金額以下の損害では保険金が支払われないことが一般的です。
たとえば免責額が20万円に設定されている場合、台風や大雨でブロック塀やフェンスが一部破損し、修理費が15万円程度なら保険金は受け取れません。
大規模な倒壊でなければ対象外となるケースもあるため、契約時に免責額をしっかり確認しておくことが大切です。
5-5.大雨・台風の被害の記録を残すことが大切
火災保険でブロック塀やフェンスの修理費用を請求する際には、被害の状況を記録として残しておくことが大切です。
台風や大雨の直後は混乱しがちですが、写真や動画を撮影しておけば、保険会社に被害の実態を正確に伝えられます。
撮影する際は倒壊した塀だけでなく、周囲の浸水状況や風による被害の痕跡も記録しておくことが大切です。
まとめ.
 大雨や台風の被害から住まいを守るためには、ブロック塀の点検と対策を怠らないことが大切です。
大雨や台風の被害から住まいを守るためには、ブロック塀の点検と対策を怠らないことが大切です。
老朽化したブロック塀は強風や豪雨で倒壊する危険が高まり、周囲への被害や事故につながる恐れがあります。
事前の対策だけでなく設置後の点検も徹底し、自宅や家族、さらに近隣の方の命を守る行動を意識する必要があります。
筆者:外構工事職人歴20年・石川公宣