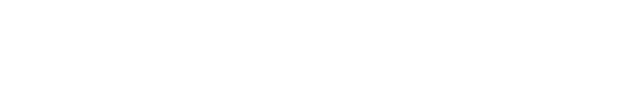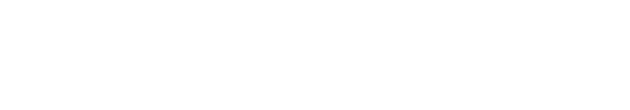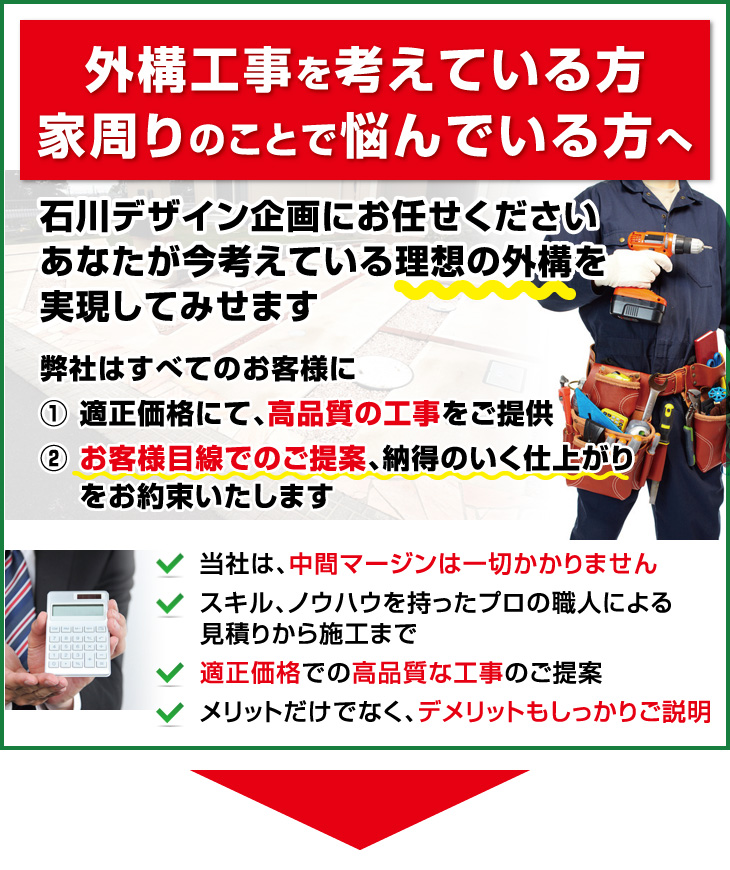仕切りや目隠しなどの役に立つ外構設備として多くの方が取り入れているのがフェンスです。
フェンスはエクステリアとしてデザイン性が高いものも多いですが、台風や大雨の際には倒壊などに注意する必要があります。
本記事では、フェンスの台風、大雨対策を詳しく解説します。
自宅やオフィスなどにフェンスを設置している方は、事前にしっかり対策をしておくことが大切です。
目次
1.台風・大雨でフェンスが倒れる・壊れる原因
 台風や大雨の際にフェンスが倒れる・壊れる原因は、一つではなく複数の要素が重なって起こることが多いです。
台風や大雨の際にフェンスが倒れる・壊れる原因は、一つではなく複数の要素が重なって起こることが多いです。
- 強風による圧力
- 地盤・基礎の弱さ
- 経年劣化
- 施工不良
このような要因が重なると、普段は問題のないフェンスでも一気に倒壊してしまいます。
とくに近年は大型台風やゲリラ豪雨が増えているため、フェンスにかかる負担も増大しています。
フェンスが倒壊すれば自宅だけでなく隣家や歩行者に被害を与える恐れもあり、重大なトラブルにつながります。原因を理解し、日頃から点検・補強しておくことが安全につながるポイントです。
1-1.強度による圧力
フェンスが台風で壊れる大きな原因は、強風による圧力です。フェンスは面の広い構造が多いため、台風の暴風が直撃すると「風の壁」となり、通常以上の負荷がかかります。
とくに高さのあるフェンスや目隠しタイプのフェンスは、風の逃げ場が少なく、倒壊リスクが高まります。
また、大雨を伴う台風では風と雨の複合的な力が加わり、固定部分や支柱に強いストレスを与えます。
強風による破損を防ぐためには、耐風性の高いフェンス材を選び、柱や基礎部分をしっかり補強しておくことが大切です。
1-2.地盤・基礎の弱さ
台風や大雨の影響でフェンスが倒れる大きな要因の一つが、地盤や基礎の弱さです。
長時間の降雨によって地盤が緩むと、支柱を支えているコンクリートや土台が不安定になり、強風に耐えられなくなります。
とくに古い住宅やDIYで設置されたフェンスは、基礎の深さやコンクリートの強度が不足しているケースが多く、大雨後にぐらつきや傾きが見られることがあります。
フェンスの耐久性を高めるには、設置段階でしっかりと基礎を固めることが重要です。既存のフェンスでも、基礎周りの点検・補修を行うことで台風被害を防ぎやすくなります。
1-3.経年劣化
フェンスは屋外に設置されているため、常に雨風や紫外線にさらされ、年月とともに劣化していきます。
木製フェンスは腐食、金属フェンスはサビ、樹脂製フェンスはひび割れなど、それぞれの素材特有の経年劣化が進行します。
普段は目立たない小さなひびやサビでも、台風や大雨によって一気に破損が広がる危険があります。とくに支柱や接合部が弱っていると、強風時に大きな力がかかり倒壊につながります。
定期的な塗装や防水処理、交換などのメンテナンスを行い、劣化を早めに発見・対策することが台風対策には欠かせません。
1-4.施工不良
フェンスが台風や大雨で倒れる原因として意外と多いのが、施工不良です。支柱の埋め込みが浅い、コンクリート基礎が不十分、水平や垂直が取れていないなど、設置時の不備があると、強風や雨の影響で簡単にぐらつきや傾きが発生します。
見た目には問題がなくても、台風シーズンに被害が集中するのはこうした施工不良が原因であることも少なくありません。
フェンスを設置・修理する際は、信頼できる専門業者に依頼し、施工品質を重視することが大切です。
2.台風・大雨に強いフェンスの種類は?
素材によってメリット、デメリットは異なるので、台風が多いエリアなど自宅ではどの素材のフェンスが最適かをチェックしておく必要があります。
2-1.アルミ
アルミのフェンスの特徴は、以下のとおりです。
- 耐久性が高い
- 錆びにくく手間が少ない
- 強度が高い
耐久性、強度が高く台風対策に選ぶフェンスの素材としてはぴったりです。軽量なので、万が一倒壊したとしても被害を最小限に抑えやすいというメリットもあります。
ただし、見た目が冷たい印象を与えるものが多いので、温かみのある印象のエクステリアにしたい方は色選びを工夫したり、存在感の少ないものにしたりといった工夫が欠かせません。
2-2.スチール
スチールのフェンスの特徴は、以下のとおりです。
- 耐久性が高い
- 錆びにくく手間が少ない
- 強度が高い
- アルミより安価
アルミと同様台風や大雨対策に適した素材ですが、アルミよりも重量があるため、倒壊対策を徹底する必要があります。
重たい分風の影響を受けにくいという点はメリットです。ただし強風を真横から受けると思わぬ被害につながる可能性があるので、倒壊対策はきちんとしておく必要があります。
2-3.木製
木製のフェンスの特徴は、以下のとおりです。
- 耐久性は中程度
- 定期的な防腐処理が必要
- おしゃれでナチュラル
木製のフェンスは、それだけで温かみを与えられるため人気の素材です。
一方で、腐食しやすく、放置していると劣化が進んで倒壊の危険性が高まります。
木目のペイントが施されたアルミのフェンスなどもあるので、本物の木製に強いこだわりがない場合はそちらも検討してみることがおすすめです。
2-4.樹脂製
樹脂製のフェンスの特徴は、以下のとおりです。
- 耐久性は中程度
- デザイン性が高い
- 軽量で扱いやすい
樹脂製のフェンスは軽量で安価、かつ強度もそれなりに維持できるので、外構におすすめです。
ただしアルミやスチールと比べると強度は劣るため、大きな台風や大雨の際には倒壊などの危険性があることは理解しておくことが大切です。
樹脂製は自由度が高く木目のプリントが施された安価なものなども多いので、台風や大雨対策も高いデザイン性も取り入れたいという方はチェックしてみることもおすすめです。
3.フェンス設置時にできる台風・大雨対策
 フェンスは家の外観を整えるだけでなく、防犯やプライバシー確保など大切な役割を担っています。
フェンスは家の外観を整えるだけでなく、防犯やプライバシー確保など大切な役割を担っています。
しかし、台風や大雨といった自然災害の影響を受けやすい外構設備でもあるため、設置時から対策を意識することが欠かせません。
フェンス設置時にできる台風・大雨対策は、おもに以下があります。
- 支柱の基礎をしっかり固める
- 風を通すデザインを選ぶ
- 防錆・防腐処理を施す
- 排水を考慮した設置場所を選ぶ
- 支柱間隔や補強を強めに設計する
それぞれの理由や具体的な対策方法を解説します。
3-1.支柱の基礎をしっかり固める
台風や大雨に強いフェンスをつくるうえでもっとも重要なのが、支柱の基礎部分です。
フェンスはパネルや板の面積が大きいため、強風が吹き付けると想像以上の圧力が支柱にかかります。
支柱が浅く埋められている場合、地盤が大雨で緩んだときに簡単に傾いたり倒れたりしてしまいます。そのため、設置時には支柱を十分な深さまで地中に埋め込み、コンクリートでしっかり固めることが大切です。
高さのある目隠しフェンスや重量のある素材はとくに負荷が大きいため、基礎が弱いと被害が拡大するリスクがあります。
3-2.風を通すデザインを選ぶ
フェンスを設置する際、デザインの選び方は台風や大雨への耐久性を左右します。
完全に隙間のないパネル型や板塀タイプはプライバシーを守る効果が高い一方で、風を遮断するため強風時には大きな圧力を受けやすく、支柱や基礎部分に大きな負荷がかかります。
台風の強風が直撃すると、倒壊や破損の原因になりかねません。
その点、ルーバーフェンスやメッシュフェンスなど風を通す構造であれば、風圧を逃がすことができるため安全性が高まります。
3-3.防錆・防腐処理を施す
フェンスは屋外に常設されるため、台風や大雨による水分の影響を常に受けます。
たとえばスチール製のフェンスは錆びやすく、錆が進行すると支柱やパネルがもろくなり、強風で簡単に破損する恐れがあります。
木製フェンスは腐食が進むと支柱の強度が低下し、台風のたびに倒壊リスクが高まります。
設置時には、防錆塗装や防腐剤の塗布、防水加工をしっかり行うことが大切です。
処理を施しておけば劣化の進行を遅らせ、台風や大雨が来ても耐えられる強度を長期間保てます。
3-4.排水を考慮した設置場所を選ぶ
フェンスはどこに設置しても同じように見えますが、実は設置場所によって耐久性や台風・大雨への強さが大きく変わります。
排水が悪い場所や水が溜まりやすい場所に施工すると、大雨で地盤が緩み、支柱がぐらついて倒壊の原因となります。とくに庭の低い場所や雨水が集中する位置は注意が必要です。
設置前に土地の勾配を確認し、水がスムーズに流れるルートを確保することが大切です。
3-5.支柱間隔や補強を強めに設計する
フェンスを設計する際、支柱の間隔や補強方法を工夫することは台風や大雨対策に直結します。
支柱の間隔が広すぎると、一つひとつの支柱に強風時の負荷が集中しやすく、倒壊のリスクが高まります。
設置段階で支柱を通常より狭い間隔で配置すれば、力が分散され安定性が向上します。
また、横桟や補強金具を追加すれば全体の強度がさらに高まり、強風でフェンスが揺れるのを防げます。
4.設置済みのフェンスにできる台風・大雨対策
 すでにフェンスを設置している場合でも、追加で台風や大雨の対策を施すことは可能です。
すでにフェンスを設置している場合でも、追加で台風や大雨の対策を施すことは可能です。
以下のような点を意識して、万が一の被害に備えられるようにしておくことが大切です。
- 定期的に基礎の点検をする
- 補助金具や控え柱を追加する
- フェンス面の風圧を減らす
- 防錆・防腐のメンテナンスをする
それぞれのポイントを詳しく解説します。
4-1.定期的に基礎の点検をする
設置済みのフェンスでも、台風や大雨に備えるためには基礎の定期点検が欠かせません。
雨水の浸透や地盤の沈下により、支柱がぐらついたり傾いたりしている場合があります。大雨の後や季節ごとに点検すれば、地盤やコンクリートのひび割れ、支柱の傾きを早期に発見できます。
問題があれば早めに補修することで、フェンスが強風に耐えられる状態を維持できます。また、点検の際には支柱の周囲に水が溜まっていないかも確認すると、台風シーズン前の安全性が高まります。
4-2.補助金具や控え柱を追加する
既存のフェンスに補助金具や控え柱を取り付けることで、台風や大雨に対する耐久性を大幅に高められます。
支柱だけでは風圧や地盤の揺れに弱い場合がありますが、補助金具や控え柱を追加することで力を分散し、倒壊リスクを減らせます。とくに高さのあるフェンスや風を遮る目隠しフェンスでは有効です。
DIYで追加することも可能ですが、専門業者に依頼することで施工精度が高まるため、台風対策としてはおすすめです。
4-3.フェンス面の風圧を減らす
設置済みのフェンスは風を遮る面が大きいほど、台風や強風で受ける圧力が大きくなります。
風圧を減らすためには、風を通しやすい構造に改良する方法があります。
たとえば、フェンスの一部をメッシュ状に変更したり、ルーバータイプのパネルを取り入れたりすると、風の力が逃げやすくなります。
また、隙間を増やすことで支柱や基礎にかかる負荷を軽減でき、倒壊や破損を防げます。
4-4.防錆・防腐のメンテナンスをする
フェンスの耐久性を保つには、設置後も定期的な防錆・防腐メンテナンスが必要です。
金属製フェンスは錆びが進行すると強度が低下し、台風や大雨で破損しやすくなります。
木製フェンスは腐食やシロアリ被害が進むと支柱がもろくなり、強風時の倒壊リスクが高まります。
設置済みフェンスでも、防錆塗装や防腐剤、塗装の塗り直しを定期的に行うことで、素材の劣化を遅らせ、長期的に安全性を確保できます。
5.台風・大雨でフェンスが倒れたらどうする?
 台風や大雨でフェンスが壊れた場合は、まず安全を最優先に行動することが大切です。
台風や大雨でフェンスが壊れた場合は、まず安全を最優先に行動することが大切です。
飛散した破片や倒れかけた支柱は非常に危険で、触れると怪我をする可能性があります。
さらに壊れたフェンスは通行人や近隣住宅に被害を与えるリスクもあるため、状況を冷静に確認したうえで以下の対応を取る必要があります。
- 周辺の安全を確保する
- 被害状況を確認する
- 写真や動画で記録を取る
- 応急処置をする
- 早急に修理・交換する
焦って自己判断で撤去や移動を行うと二次被害や怪我の原因になるため、まずは周囲の安全を確保し、必要に応じて家族や近隣に注意を促すことから始めることが大切です。
5-1.周囲の安全を確保する
フェンスが倒れたり破損したりした場合、周囲の安全確保が最優先です。
飛び出した支柱や割れたパネル、破片は風で飛散する可能性があり、通行人や近隣住民に危険を及ぼします。
まずはその区域に立ち入らないようにし、バリケードや目印を置いて注意喚起することが重要です。
また、倒れたフェンスの下に物や人がいないかも確認する必要があります。
周辺の安全を確保しておくことで、二次被害や怪我のリスクを防ぎ、修理や撤去作業を安全に進めやすくなります。
5-2.被害状況を確認する
フェンスの破損状況の把握は、修理や保険申請の第一歩です。
支柱が折れているのか、パネルが割れているのか、基礎に被害が出ているのかを確認する必要があります。
倒壊している場合は無理に触れず、危険を避けながら状況を観察することがおすすめです。また、被害範囲や程度を確認することで、応急処置や専門業者への依頼範囲を明確にできます。
台風や大雨の後は追加の風や雨による二次被害も考えられるため、周囲の安全を確認しながら冷静に被害状況を把握することが大切です。
5-3.写真や動画で記録をとる
壊れたフェンスの状況は、修理や保険請求のために写真や動画で記録しておくことがおすすめです。
破損した支柱、割れたパネル、基礎の状況を複数の角度から撮影し、被害の全体像を残しておくと、専門業者による見積もりや保険会社の申請がスムーズになります。
また、壊れた部品や散乱物も記録しておくと、後から整理や修理の優先順位を決める際に役立ちます。
5-4.応急処置をする
フェンスが壊れた場合、修理までの間に応急処置を行うことで二次被害を防ぎやすくなります。
倒れかけた支柱はロープや固定具で仮止めし、飛散したパネルは安全な場所に移動させる必要があります。
木製や金属製の破片には鋭利な部分があるため、手袋や保護具を着用して作業することが大切です。
ただし、大掛かりな撤去や修理は素人が行うと危険を伴うため、あくまで一時的な対策に留め、専門業者に修理を依頼できるまでの安全措置として行うことがおすすめです。
5-5.早急に修理・交換をする
応急処置の後は、壊れたフェンスの早急な修理や交換が必要です。
支柱やパネルの破損は放置すると風や雨の影響でさらに被害が拡大する可能性があります。
とくに台風シーズンが続く場合や雨量の多い地域では、損傷したままのフェンスが再度倒壊する危険があります。
信頼できる施工業者に依頼し、基礎や支柱の強化、防錆・防腐処理も併せて行うと、次回の台風や大雨に対する耐久性が向上します。
まとめ.
 フェンスは単なる境界線ではなく、台風や大雨による被害から家や庭を守る重要な役割を持っています。
フェンスは単なる境界線ではなく、台風や大雨による被害から家や庭を守る重要な役割を持っています。
半面台風や大雨の影響で破損や倒壊のリスクも高いため、事前にしっかり対策をしておくことが大切です。
事前の対策だけでなく定期的なメンテナンスも徹底すれば、強風や豪雨でも安心して暮らせる外構を作ることが可能です。
筆者:外構工事職人歴20年・石川公宣