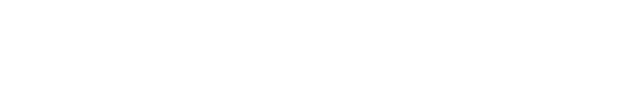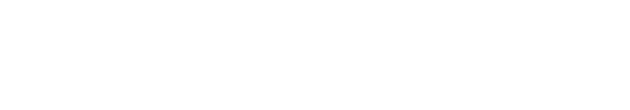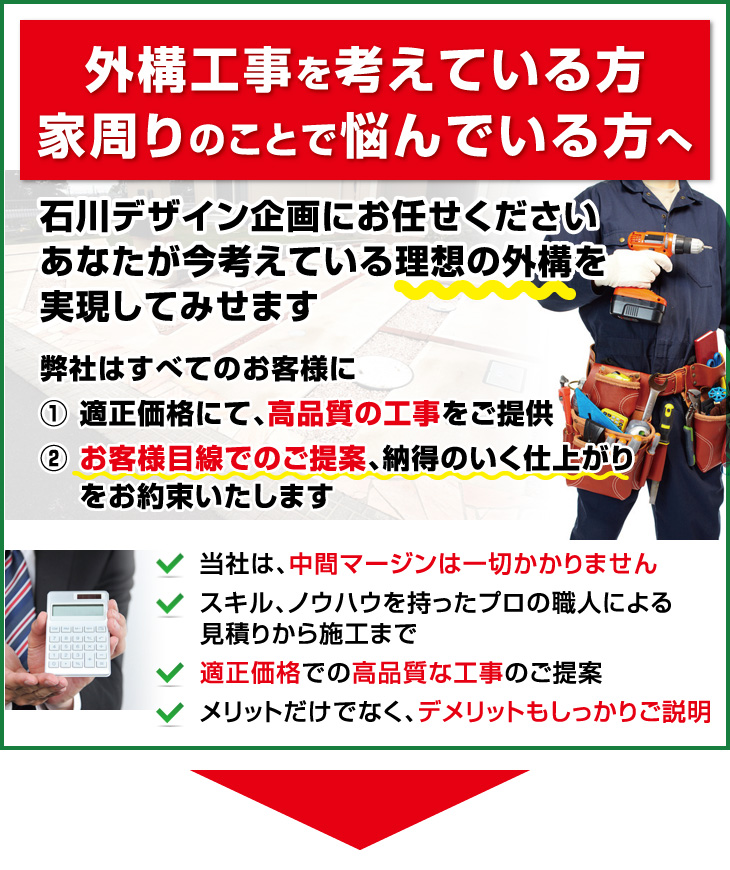近年、台風による強風や豪雨の影響でブロック塀の倒壊が相次ぎ、周囲の住宅や通行人に被害が及ぶケースが増えています。
とくに築年数が経過したブロック塀は、基礎や補強の不備が原因で倒れやすくなっています。万が一倒壊してしまった場合に備えて、火災保険が使えるかどうかについても考えておくことも大切です。
この記事では、台風によるブロック塀の倒壊を防ぐための具体的な対策や、火災保険の対象になるかなどについて解説します。自宅の安全を守るために、ブロック塀の点検や補修を定期的におこない、災害に強い外構環境を整えていきましょう。
目次
1.台風でブロック塀が倒壊するのを防ぐ対策5選
 強風や豪雨によるブロック塀の倒壊は、自分の家庭だけでなく周囲の人や物にも被害を与える危険な問題です。
強風や豪雨によるブロック塀の倒壊は、自分の家庭だけでなく周囲の人や物にも被害を与える危険な問題です。
とくに背の高いブロック塀や老朽化したブロック塀は、台風の風圧に耐えられず、倒れる危険性が高いです。
ここでは、台風によるブロック塀の倒壊を防ぐためにできる5つの対策を紹介します。家族の安全を守り、隣家や通行人への被害を未然に防ぐためにも、これらの対策を早めに取り入れることが大切です。
1-1.控え壁を設置する
控え壁とは、ブロック塀の強度を高めるために垂直に取り付ける補助的な壁のことです。台風時に塀が横から受ける風圧を分散させ、倒壊を防ぐ役割があります。
建築基準法でも、一定の高さを超えるブロック塀には控え壁の設置が義務付けられており、安全対策として非常に重視されています。
塀が長く連続している場合は、一定間隔ごとに控え壁を設置することで安定性が高まります。既存の塀にも後付けで施工が可能なので、台風シーズン前の補強としておすすめです。
1-2.鉄筋の配置と補強に気を付ける
ブロック塀の内部に鉄筋を正しく配置し、しっかりと固定することは構造強度を高めるための基本です。
鉄筋が入っていない塀や、サビや腐食によって劣化した鉄筋は、台風時に耐えきれず倒壊する危険性が高まります。正しい鉄筋配置には、縦横方向への配筋、結束、コンクリートの充填が必要です。
特に古いブロック塀は、鉄筋の施工が不十分なことが多いため、外構工事業者に相談して点検と補強工事をしてもらうことも検討する必要があります。
1-3.老朽化したブロック塀は補修する
ブロック塀が経年劣化していると、台風の風圧や雨水による浸食に弱くなり、倒壊の危険が高まります。
ひび割れ、傾き、モルタルの剥がれなどの症状が見られたら、早めに補修または交換する必要があります。
老朽化が進んだ塀は、見た目ではわかりにくい内部の損傷が進んでいることもあります。
不安な場合は、専門業者に調査と定期的なメンテナンスをお願いするのもおすすめです。
1-4.ブロック塀の高さを低めにする
ブロック塀は、高ければ高いほど風の影響を受けやすくなります。台風に備えるなら、高さを制限することも大切です。
現在の建築基準法ではブロック塀は2.2メートル以下にするよう定められていますが、さらに安全を考慮するなら1.2〜1.5メートル程度に抑えるのが望ましいです。
高さを下げることで重心が安定し、台風などによる倒壊の危険を避けやすくなります。
1-5.ブロック塀の素材を軽量にする
近年では、軽量コンクリートブロックや樹脂製パネルなど、従来よりも軽くて耐久性のある素材が多く登場しています。
軽量な素材を使用することで、万が一倒壊した場合の被害を最小限に抑えることも可能です。
また、軽量素材は施工もしやすく、コストを抑えながら台風対策できるという点もメリットです。
新設やリフォームの際には、見た目と安全性のバランスを考えて素材を選んでみましょう。
2.台風で倒壊する恐れのあるブロック塀の見分け方
 近年の台風は大型化・長時間化しており、強風や大雨による被害も深刻化しています。とくに倒壊のリスクが高いのが、古い構造のブロック塀です。
近年の台風は大型化・長時間化しており、強風や大雨による被害も深刻化しています。とくに倒壊のリスクが高いのが、古い構造のブロック塀です。
倒壊すると隣接する建物や歩行者に大きな被害を与える恐れがあるため、定期的な点検とメンテナンスが必要です。
台風前には、塀の高さや傾き、ひび割れの有無、控え壁の設置状況などを確認しましょう。
目視できる異常があれば早めに補修・改修することが、安全な住環境づくりにつながります。
ここでは、台風で倒れやすいブロック塀の見分け方について詳しく解説します。
2-1.高さが基準を超えている
ブロック塀の高さは、建築基準法により2.2メートル以下と定められています。これを超えると風圧を受けやすくなり、台風の強風で倒壊するリスクが非常に高まります。
とくに基礎が浅い古い塀や、鉄筋が入っていない塀では、高さが規定内でも危険です。安全のためには、塀の高さを1.2〜1.5メートル程度に抑えるのが理想です。
目視で測るのが難しい場合は、専門業者に点検を依頼しましょう。
もし高さが基準を超えている場合は、上部を撤去するなどの対策を取る必要があります。自宅のブロック塀が基準を満たしているか、台風シーズン前に必ず確認しましょう。
2-2.控え壁が設置されていない
一定の高さを超えるブロック塀には、風による転倒を防ぐために控え壁の設置が法律で義務付けられています。
控え壁は、塀の背面にL字型で取り付ける補助構造で、塀の安定性を高める役割があります。台風のような突風が吹いた際、控え壁があれば圧力を分散でき、倒壊を防ぎやすくなります。
控え壁は、塀の長さ3.4メートル以内ごとに1つ設けるのが基本とされています。もしご自宅のブロック塀に控え壁が見当たらない場合は、早急に外構工事業者に相談し、控え壁を設置してもらうようにしましょう。
2-3.ひび割れや傾きがある
ブロック塀のひび割れや傾きは、構造的な劣化が進んでいるサインです。
台風時の強風や揺れにより、ひび割れや傾きがあるブロック塀は倒壊の危険が高まります。ひび割れが広がっている、ブロックの接合部にズレが見られる、塀全体が前後どちらかに傾いているなどの症状があれば、非常に危険です。
また、内部の鉄筋が腐食しているケースもあり、見た目以上に脆弱な状態になっている可能性もあります。
少しの異常でも早めに対応することで、台風による大きな被害を未然に防ぐことができます。
3.台風でブロック塀が倒壊したら火災保険は使える?
 台風の強風によってブロック塀が倒壊した場合、条件を満たせば火災保険で補償される可能性があります。ただし、すべてのケースで保険が適用されるわけではありません。
台風の強風によってブロック塀が倒壊した場合、条件を満たせば火災保険で補償される可能性があります。ただし、すべてのケースで保険が適用されるわけではありません。
とくにブロック塀は建物本体とは別物とみなされることもあるため、加入している火災保険の内容をしっかり確認することが大切です。
近年は台風による風災被害が増えており、こうした災害リスクに備える意味でも、保険の見直しや塀の補強を検討しておくことをおすすめします。
ブロック塀が古くなっている場合は、倒壊のリスクも高まるため、点検と併せて保険適用の有無を事前に確認しておきましょう。
3-1.風災補償が付帯されているかを確認
火災保険に加入していても、台風によるブロック塀の倒壊が補償されるかどうかは、「風災補償」が含まれているかによって変わります。
風災補償とは、台風や突風、竜巻など風による自然災害に対応する保険のことで、これが付帯されていなければ補償対象外となることが多いです。
契約内容を見直し、自宅のブロック塀が補償の範囲に含まれているか確認しておく必要があります。
また、風災補償には一定の条件や免責金額が設定されている場合もあるため、細かい規定まで把握しておくことも忘れないことが大切です。
3-2.ブロック塀が建物に付属していると認められるか
火災保険で台風によるブロック塀の倒壊が補償されるかどうかは、その塀が「建物に付属している構造物」と認められるかが重要な判断基準です。
たとえば、住宅の門柱や門扉と一体化している場合や、敷地を囲う機能が明確な塀であれば、保険適用の対象になる可能性があります。
逆に、庭の装飾的な塀や独立して設置された塀は対象外になることもあります。
保険会社によって判断が異なるため、不明点があればあらかじめ保険会社に問い合わせてみましょう。
3-3.免責金額(自己負担)に注意
火災保険の多くには「免責金額」が設定されており、一定額までは自己負担になる点に注意が必要です。
たとえば、免責金額が10万円で、台風によるブロック塀の修理費用が8万円だった場合、保険金は支払われません。
保険が適用されても実際には自己負担になるケースも少なくありません。とくにブロック塀は修理費用が比較的低く抑えられることもあるため、免責金額の設定によっては保険を使えない場合があります。
補償の有無だけでなく、免責金額の条件まで事前に確認しておくことで、いざというときの金銭的な負担を防げます。
3-4.被害状況を写真などで証明する
台風でブロック塀が倒壊した際に火災保険を申請する場合、損害状況を証明するための写真や修理見積書が必要になります。
被害を受けた直後に現場の状況を撮影し、倒壊の範囲や程度が分かるように記録しておきましょう。ブロックが崩れた様子や、倒壊によって周囲に被害が及んでいる箇所などを、角度を変えて撮影するのがポイントです。
また、可能であれば修理業者による点検報告書なども提出すると、保険金の審査がスムーズになります。申請のタイミングを逃さないよう、被害を受けたら早めに保険会社に連絡し、必要書類の案内を受けるようにしましょう。
3-5.経年劣化による倒壊は対象外
火災保険では、台風の強風など明確な自然災害が原因と認められる場合に限り、ブロック塀の倒壊が補償されます。
逆に、老朽化や施工不良など経年劣化が原因と判断された場合は、保険金が支払われないケースがほとんどです。
ブロック塀が古くなってひび割れや傾きが生じている状態で倒壊した場合、保険会社は自然災害ではなく構造的欠陥や放置が原因と見なすことがあります。
そのため、定期的な点検と補修をして、保険が適用される条件を満たしておくことが大切です。
4.古いブロック塀を台風などで倒壊させないための予防策

台風の強風や豪雨は、老朽化したブロック塀の倒壊の原因になってしまいます。
特に1981年以前に建てられた古い塀は、構造が現在の基準に合っておらず、倒壊の危険性が高まります。台風シーズン前に点検をおこない、控え壁や鉄筋、基礎部分の補強を検討しましょう。
ブロック塀は長期間放置すると、内部の鉄筋が腐食したり、モルタルが劣化して接合部が弱くなることがあります。事前の対策として、控え壁の追加や鉄筋の再配置、基礎の打ち直し、高さの見直しなどをすれば、安全性が高まるでしょう。
この項では古いブロック塀が台風などで倒壊しないための予防策を解説します。
4-1.控え壁を追加で設置する
控え壁は、ブロック塀が横方向の力に耐えるために必要な構造です。
台風時の強風は想像以上に大きな圧力をブロック塀に与えるため、控え壁がないブロック塀は倒壊の危険性が高くなります。
現在の建築基準法では、高さ1.2メートル以上のブロック塀には、3.4メートルごとに控え壁を設けることが求められています。
古いブロック塀にはこの基準が適用されていないケースが多いので、追加で控え壁を設置して耐風性能を高めましょう。
台風による被害を未然に防ぐためにも、まずは控え壁の有無と設置間隔を確認し、不足があれば早急に補強工事を検討してみてください。
4-2.鉄筋の有無と腐食のチェック・補強
ブロック塀内部に鉄筋が入っていない、または腐食している場合、台風時に倒壊する危険性が高くなります。
鉄筋は塀の強度を保つための重要な要素で、風圧や振動に耐えるためには欠かせません。
古いブロック塀では施工当時に鉄筋が入っていないことも多く、また経年劣化により錆びて脆くなっている場合もあります。
点検では、鉄筋の有無を非破壊検査やコア抜きで確認し、必要に応じて補強や再構築をおこないます。
補強工事では、外側から鉄筋を追加して補強したり、一部を解体して鉄筋入りの新しいブロック塀に置き換えたりといった方法があります。
4-3.基礎の補強または打ち直し
どれだけ表面のブロック塀を補強しても、基礎がしっかりしていなければ意味がありません。
基礎とは、ブロック塀の土台となるコンクリート部分で、十分な厚みや深さがないと、台風の強風で簡単に倒れてしまう恐れがあります。
とくに古いブロック塀では、基礎が浅い、無筋コンクリートである、あるいは地中に十分に埋設されていないなどの問題がよく見られます。
こうした場合、基礎の補強工事や全面的な打ち直しが必要です。新しい基礎を設ける際には、地中30cm以上に埋め込む設計が一般的で、アンカーボルトや鉄筋を使って倒壊しにくいブロック塀に仕上げていきます。
自分でDIYなどをするのは難しい作業なので、プロに相談して早めに対処してもらいましょう。
4-4.高さの低減やフェンスへの改修
ブロック塀は高くなればなるほど風圧を受けやすく、台風の際に倒壊しやすくなります。とくに高さが2メートルを超える塀は、風による被害のリスクが大きく、建築基準法でも最大2.2メートルまでと定められています。
対策としては、塀の上部を一部撤去して高さを下げたり、軽量素材であるアルミフェンスなどに切り替える方法があります。
最近では、下部にブロックを使用し、上部は風通しの良いフェンスにするハイブリッド構造の塀も人気です。
見た目もすっきりし、圧迫感を軽減できるうえ、通気性も高まるため、防犯や快適性の面でもメリットがあります。古い高い塀は倒壊のリスクを高めるため、台風前に高さの見直しを検討しましょう。
まとめ.
 ブロック塀は台風による被害を受けやすく、万が一倒壊すると人や建物、車などに重大な被害を与えてしまいます。
ブロック塀は台風による被害を受けやすく、万が一倒壊すると人や建物、車などに重大な被害を与えてしまいます。
ブロック塀を新たに設置する際は法律で定められた基準を守るだけでなく、より安全性を高める工夫を取り入れることも大切です。
ブロック塀の設置やメンテナンスなどは、外構工事業者に相談してみましょう。最新の軽量素材の提案や基礎、土台作り、メンテナンスなどをサポートしてくれるので、安心してお任せできます。
自宅のブロック塀が古い、傾いている気がするなど、まずは気軽に問い合わせてみてください。
筆者:外構工事職人歴20年・石川公宣