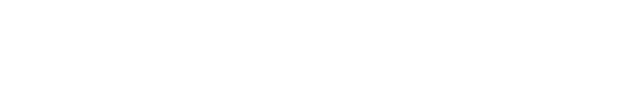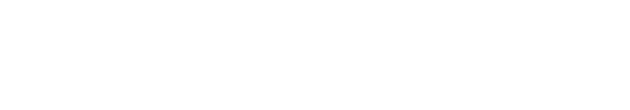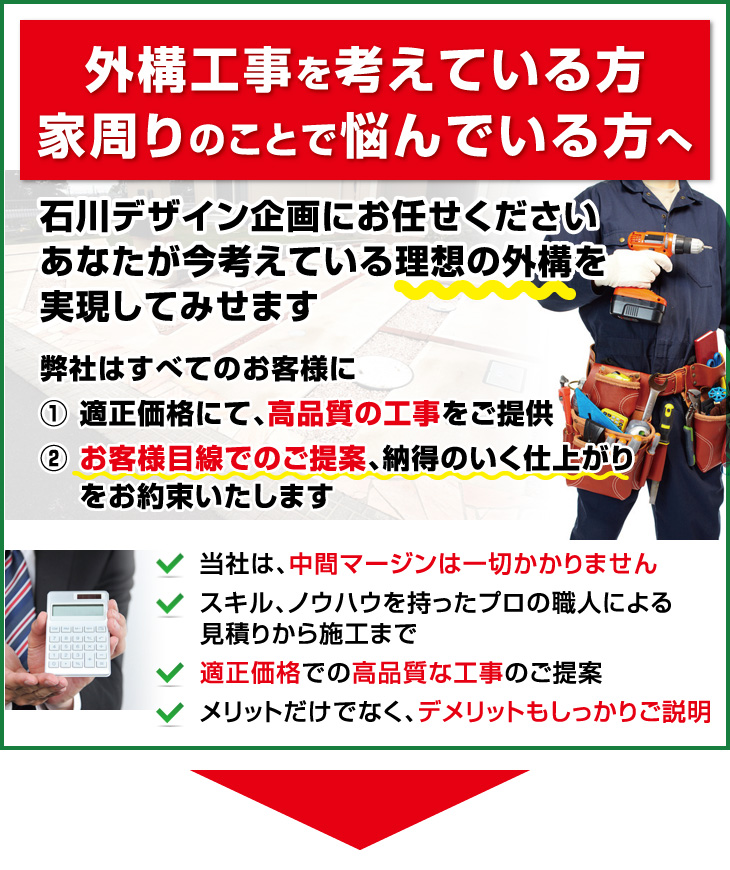開放感のあるオープン外構を選ぶ人が増えています。
せまい敷地でも広く感じられ、明るい家づくりができると人気です。
おしゃれな雰囲気に満足している人が多い一方で、後悔している人もいます。
おしゃれなデザインにしたはずなのに、なぜ後悔することになってしまったのでしょうか。
失敗を避けるためにはオープン外構のメリットだけでなくデメリットも知り、どのような対策をすればよいのか確認しておきましょう。
目次
1.オープン外構とは
 欧米の郊外にある住宅のような、開放感のあるエクステリアデザインをオープン外構といいます。
欧米の郊外にある住宅のような、開放感のあるエクステリアデザインをオープン外構といいます。
塀やフェンス、門扉といった囲いを設置しないため、広く見渡せる明るい雰囲気になるのが特徴です。
隣の家や道路とは異なる素材のコンクリートにしたり、タイルにしたりして境界を明確にします。
道路との違いがわかりやすい芝生にすることも多いでしょう。背の低い植栽で境界を作ることもあります。
視界をさえぎるものがなく、敷地内をよく見渡せるエクステリアデザインです。
2.オープン外構とセミクローズ外構はどう違う?
 セミクローズ外構はオープン外構と似ていますが、敷地内のすべてを開放的なデザインにはしません。
セミクローズ外構はオープン外構と似ていますが、敷地内のすべてを開放的なデザインにはしません。
セミクローズ外構は、ひと昔前のエクステリアデザインとしてよく見られたクローズ外構と、最近人気のオープン外構の中間的なデザインといえます。
クローズ外構とは高い塀やフェンスを設け、敷地内への視界をさえぎったエクステリアデザインです。
隣家や家の前の道路から視線を感じることなく過ごせます。
洗濯物を干したり、子どもやペットの飛び出しを防いだり、プライバシー保護や防犯性の確保に役立っていました。
しかし、完全に囲ってしまうため暗さを感じるのがデメリットです。
また、高い塀で防犯性を高めていることが裏目になり、侵入者が隠れやすくなってしまう懸念もあります。
一方、セミクローズ外構は、部分的に視界をさえぎるものを設置しているのが特徴です。
家のなかが見えてしまうような気になる部分だけをフェンスや塀、植栽などで目隠しします。
ほかの部分はオープン外構と同じく開放的なデザインにするため、必要なところには目隠しをしながら明るい雰囲気も残せるでしょう。
3.オープン外構のメリット
オープン外構のメリットを詳しく紹介します。
3-1.開放感が魅力
 オープン外構の魅力は、なんといっても開放感があることです。圧迫感がないため、気持ちよく過ごせるでしょう。せまい敷地でも広く見えることがポイントで、家の中まで光が届きやすく明るさを感じられます。
オープン外構の魅力は、なんといっても開放感があることです。圧迫感がないため、気持ちよく過ごせるでしょう。せまい敷地でも広く見えることがポイントで、家の中まで光が届きやすく明るさを感じられます。
また、風が通り抜けやすいので、気持ちのよい家づくりができるでしょう。海外にある郊外の家のような、おしゃれな雰囲気になるところもメリットです。
背の低い樹木や草花の植栽で、敷地の境界を作りながら自然も感じられます。石畳のようにブロックを敷いたり、郵便ポストや門柱のスタイルにこだわったりするのも楽しいです。
隣の家や道路との間に視界をさえぎるものがないため、近隣とのコミュニケーションを取りやすいです。隣人や道路を歩く人ともあいさつや会話を自然に楽しめるので、顔の見える近所付き合いがしやすいです。
近所にどのような人が住んでいるのかを把握しておくことで地域の防犯対策になり、いざというときに助け合いをしやすくなるといわれています。近隣とのコミュニケーションを大事にしたい人にとって、オープン外構の開放感は大きな魅力です。
3-2.外構工事費が安く済む
 オープン外構は塀やフェンス、門扉などを設置しないため、外構工事費が安く済みます。一方でオープン外構ではない場合、家を建てるときには外構工事によって予算がオーバーしてしまったという事例も少なくありません。
オープン外構は塀やフェンス、門扉などを設置しないため、外構工事費が安く済みます。一方でオープン外構ではない場合、家を建てるときには外構工事によって予算がオーバーしてしまったという事例も少なくありません。
住宅の購入費だけを考え、外構にも予算が必要なことを忘れていたという人もいます。また、外構にかかる費用は高額になることも多いです。フェンスや門扉は高額な建材が多く、おしゃれなものを選ぶと予算を超えてしまうといったこともあります。
オープン外構を選べば塀やフェンス、門扉といった材料費や、設置するための工事費がかからないので、節約したい人に向いているでしょう。とくに、道路に面しているところが多ければ多いほど、コストダウン効果が高い傾向にあります。
4.オープン外構のデメリット
オープン外構のデメリットを紹介します。
メリットだけでなく、デメリットも知っておくことが大切です。
4-1.プライバシーを守れず外からの視線が気になる
 高い塀やフェンスで囲われていないため、プライバシーを確保するのが難しいでしょう。
高い塀やフェンスで囲われていないため、プライバシーを確保するのが難しいでしょう。
視線をさえぎるものがないので道路や近隣から見えやすく、しっかり対策をしておかないとプライバシーを守りにくいといえます。
とくに浴室は、外から見えにくい場所に設置しなければなりません。また、近隣とのコミュニケーションが取りやすい分、まわりの視線が気になり疲れてしまうこともあるかもしれません。
過ごす時間の多いリビングも、外からの視線が届かない場所にしておくとリラックスできるでしょう。オープン外構にする際は、ある程度のプライバシーが守れるような対策が必要です。
さえぎるものがないため風向きによっては、自分の家の落ち葉だけでなく外から飛んでくることもあるでしょう。
雑草や落ち葉などが見えやすいため、まわりの目が気になり、庭の手入れが欠かせなくなることが多いです。
4-2.セキュリティに不安がある
 オープン外構は道路から敷地内に侵入しやすいため、セキュリティ面での不安を感じやすい点が挙げられます。
オープン外構は道路から敷地内に侵入しやすいため、セキュリティ面での不安を感じやすい点が挙げられます。
一方で、開放的なオープン外構は敷地内全体をよく見渡せるため死角がなく、侵入者が隠れにくいという利点もあります。
隠れにくい家はターゲットになりにくいといえるものの、セキュリティ対策をするに越したことはありません。
監視カメラや感知センサー付きのライトなどを設置するといった防犯対策をしておくことが安心につながます。
5.オープン外構が向いているのはこんな人!
 敷地面積がせまい場合は、オープン外構が向いています。敷地がせまいほど、高い塀やフェンスで囲うと圧迫感や閉塞感が出やすく、家のなかに光が届きにくいため暗い印象にもなりがちです。
敷地面積がせまい場合は、オープン外構が向いています。敷地がせまいほど、高い塀やフェンスで囲うと圧迫感や閉塞感が出やすく、家のなかに光が届きにくいため暗い印象にもなりがちです。
敷地がせまくても、オープン外構なら光や風を感じやすくなり、明るい家になるでしょう。とくに郊外よりも土地が小さい傾向にある都心に家を建てる場合は、開放感のあるオープン外構がおすすめです。
また、ガーデニングが好きな人も、道を歩く人にきれいな庭を見て楽しんでもらうことができるため、オープン外構が向いているといえるでしょう。街の景観にも貢献できます。
ただし、庭の手入れを続けなければならないため、草取りをはじめとする庭仕事が好きな人でなければ難しいでしょう。施工会社に相談し、できるだけ手入れが少なく済んで、きれいな状態を維持しやすい庭にしてもらうのも一つの方法です。
高い塀やフェンスで敷地内に死角ができるよりも、近隣の目が届いたほうが安心を感じる人にも向いています。
プライバシーの確保が難しいものの、オープン外構にすると侵入者が隠れる場所がないためターゲットになりにくいです。
家を建てる予算を抑えたい人にも向いています。外構工事にかかる費用が安く済むため、その分を建物にまわしたり、ほかのこだわりたい部分に使ったりできるでしょう。
6.オープン外構によくある失敗例

オープン外構のメリット・デメリットを理解しておかないと、施工後に後悔することになる恐れがあります。オープン外構のよくある失敗例を知り、同じ轍を踏まないように気を付ける必要があります。
よくある失敗の1つ目は、洗濯物が丸見えになることです。クローズ外構やセミクローズ外構に比べて、オープン外構はプライバシーを確保しにくい特徴があります。
外部からの視線を遮れず、洗濯物が通行人に丸見えになってしまうこともあるので注意が必要です。
また、隣の家でバーベキューをしているときなど、塀を立てていないことで煙が直接流れ込み、洗濯物に臭いがついてしまうリスクもあります。
2つ目のよくある失敗例は、車の切り返しで使われることです。
オープン外構は敷地が道路と直接つながっていることも多く、車の方向転換などで使われてしまう場合があります。
その結果、エクステリアを部分的に壊されるリスクもあるので要注意です。
3つ目のよくある失敗例は、置き配が利用しにくいことです。
誰でも簡単に入ってこれる構造であるため、盗難のリスクを考えると置き配も頼みにくくなります。
7.オープン外構で失敗を避けるにはどうしたらいい?
外構工事における失敗を避けたい場合は、どのようなことに注意したらよいのでしょうか。
オープン外構で失敗しない方法を紹介します。
7-1.部分的に植栽やフェンスを取り入れる
 敷地内を通り抜けることで近道となってしまう場合には、とくに注意が必要です。子どもが通り道にしてしまい、育てた花を踏まれたり、車にキズをつけられたりといった思わぬトラブルにつながることもあります。
敷地内を通り抜けることで近道となってしまう場合には、とくに注意が必要です。子どもが通り道にしてしまい、育てた花を踏まれたり、車にキズをつけられたりといった思わぬトラブルにつながることもあります。
悪気がないとしても、気持ちがよいのもではありません。部分的に植栽や低いフェンスを設置し、敷地と道路の境界をわかりやすくするのも一つの手です。
花壇にきれいな花が咲き植栽があれば、子どもにもわかりやすいでしょう。低いフェンスがあれば、侵入を防ぐこともできます。道路と敷地に段差をつけることもわかりやすいです。
境界がわかりやすくなっていることにより、侵入されにくくなります。
駐車場スペースへの侵入を防ぎたい場合は、ポールを設置するとよいでしょう。車を置くためのスペースなので、ものがない広いスペースとなっており、子どもの遊び場になりやすいです。
道がせまいところでは車の方向転換に使われることもあり、危険性を避けるためにも対策をしておいたほうがよいでしょう。また、洗濯物を干すスペースを考えておくことも大切です。
外から見えない室内や、目が届きにくい2階のテラスなどで干している人が多い傾向にあります。難しい場合は、部分的なフェンスや植栽で視界をさえぎるセミクローズ外構を検討してみるのもよいでしょう。
7-2.施工会社としっかり打ち合わせをする
 施工会社としっかり打ち合わせをすることも大切です。おしゃれなオープン外構にしたいと伝えるだけでなく、実現したいイメージを理解してもらいましょう。
施工会社としっかり打ち合わせをすることも大切です。おしゃれなオープン外構にしたいと伝えるだけでなく、実現したいイメージを理解してもらいましょう。
好きな外構の写真を雑誌やインターネットで探し、施工会社の担当者やプランナーに見せると具体的なイメージが伝わりやすくなります。
まずは費用を気にせず、気に入ったイメージを集めましょう。施工会社にイメージを理解してもらえれば、予算内で理想に近づくように考えてもらえます。
実際に現場を見てもらい、イメージに近いエクステリアにするにはどうしたらよいのかアドバイスしてもらうのもおすすめです。プロの目がある業者ならメリットはもちろん、デメリットも教えてくれます。
多くの施工会社がありますが、信頼のおける業者を選びましょう。現地調査をしてから、どのようなプランがよいのかを決め、見積もりを出してくれる業者が安心です。
また、工務店やハウスメーカーに依頼すると、そこから外構専門業者に依頼されるので中間マージンが発生して余分な費用がかかってしまいます。
より安く済ませたい人は、業者選びにも注意しましょう。見積もりから工事までしてくれる施工会社なら、工事後のアフターフォローがしっかりしているところもあります。
8.オープン外構で講じておきたい防犯対策
オープン外構は他のタイプよりも防犯性が低いため、自分なりの対策を講じておくことが大切です。
ここでは、オープン外構で講じておきたい4つの防犯対策を紹介していきます。
8-1.防犯砂利を活用する

防犯砂利とは、上を歩くときに音が鳴るタイプの砂利のことです。いくつかの種類があるので、デザインやコストなどを検討しながら選ぶとよいでしょう。
代表的な防犯砂利には、ガラス発砲、セラミック素材、化粧砂利、白砕石といった種類があります。
ガラス発砲の防犯砂利は軽石に近く、踏むと大きな音が鳴るので防犯上効果的です。ただし、軽いので風に飛ばされたり、こすれて粉が発生したりする点には注意が必要です。
セラミック素材の防犯砂利は、踏んだときの音が高く、荷重も大きいので流出しにくい特徴があります。他の種類に比べて費用がかかるのがネックですが、エクステリアの美観も保てるのでおすすめです。
化粧砂利ベースの防犯砂利は、焼成加工によって音が高く鳴る仕様になっています。費用の安い白砕石は、厳密にいえば防犯砂利ではありませんが、上を歩けばある程度の音は鳴ります。
8-2.心理的に入りにくくする
心理的に入りにくいデザインにすることも効果的な防犯対策の一つです。
これは、構造物や植物などの配置を工夫して内側と外側を区別し、第三者に他人の敷地であることを意識させる方法です。
エクステリアのおしゃれさを保ちつつ、知らない人の侵入を防ぎたい場合は検討するとよいです。
8-3.照明を取り入れる

オープン外構の防犯対策として、照明を取り入れる方法も一定の効果が得られます。
センサーライトは人が通るたびに反応するため、不審者の侵入を断念させる効果も期待できます。
照明を増やすことでエクステリアの雰囲気もおしゃれになるので、一石二鳥の方法だといえるでしょう。
8-4.防犯カメラを設置する

敷地内に防犯カメラを設置する方法もおすすめです。
近年では、スマートフォンと連携させることで、より高い防犯効果を発揮してくれる防犯カメラも登場しています。
例えば、外出中に不審者が映り込むとスマートフォンに通知が届くといったものです。
不審者の様子を録画するだけでなく、スピーカー越しに話しかけられる製品も出てきています。
犯罪者は声をかけられると犯行を諦めやすいというデータもあり、IoT技術の進歩を活用すればより防犯効果を高められるでしょう。
9.オープン外構は後からクローズ外構にリフォームできる!
 オープン外構は、後からクローズ外構にリフォームすることも可能です。
オープン外構は、後からクローズ外構にリフォームすることも可能です。
まずは工事費が少なく済むオープン外構にしておき、ライフスタイルの変化によって必要になったときにクローズ外構へリフォームするのもよいでしょう。
最初からフェンスや塀で囲わず、外構を作り込まないことによって、庭や駐車場の使い方を変えたいといったときにリフォームしやすいです。
また、オープン外構にしておき、暮らしながら気になるところにフェンスを設置したり、植栽をしたりなど、セミクローズ外構に変化させていくこともできます。
まとめ.
 オープン外構は開放感があり、おしゃれな雰囲気になりますが、プライバシーやセキュリティなどの対策が必要です。
オープン外構は開放感があり、おしゃれな雰囲気になりますが、プライバシーやセキュリティなどの対策が必要です。
さらに、失敗を避けるためには、相談しながらイメージに近いエクステリアに近づけてくれる施工会社との出会いもポイントとなります。
正しい知識や豊かな経験をもとに、お客様の立場になって熱心に取り組んでくれる施工業者に依頼できるよう、この記事で紹介したことを参考にしてください。
筆者:外構職人歴20年・石川公宣